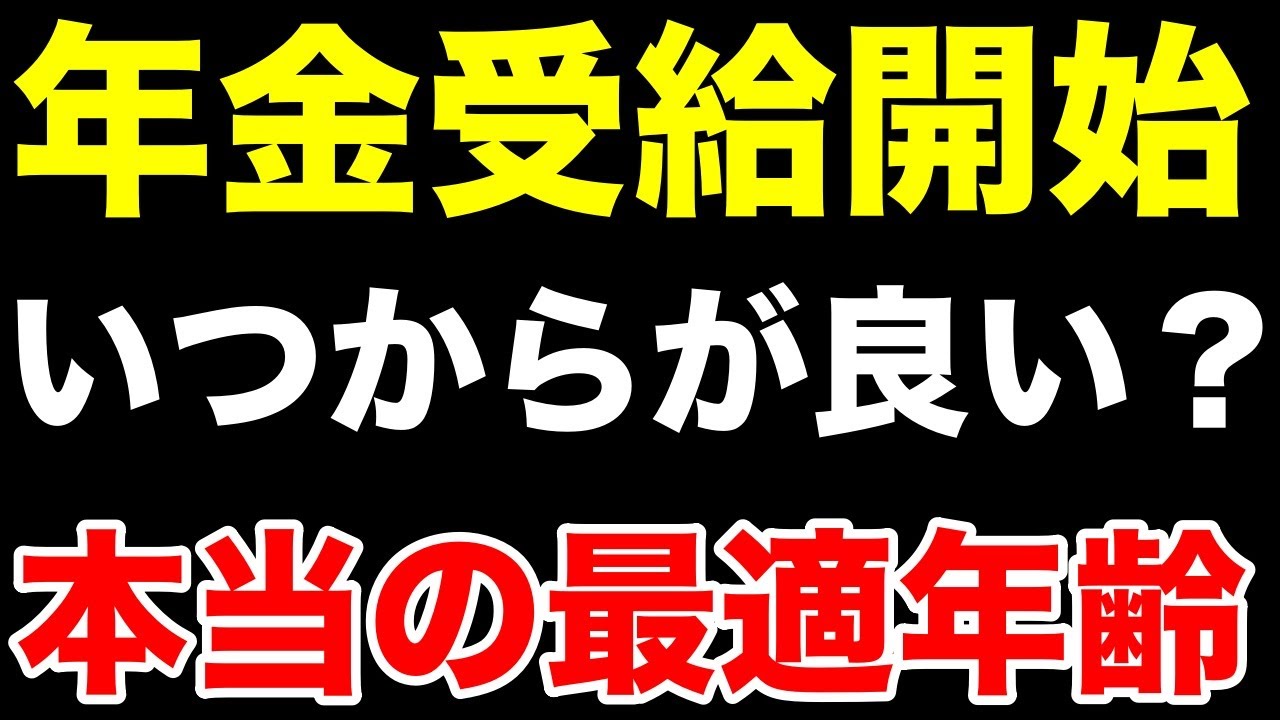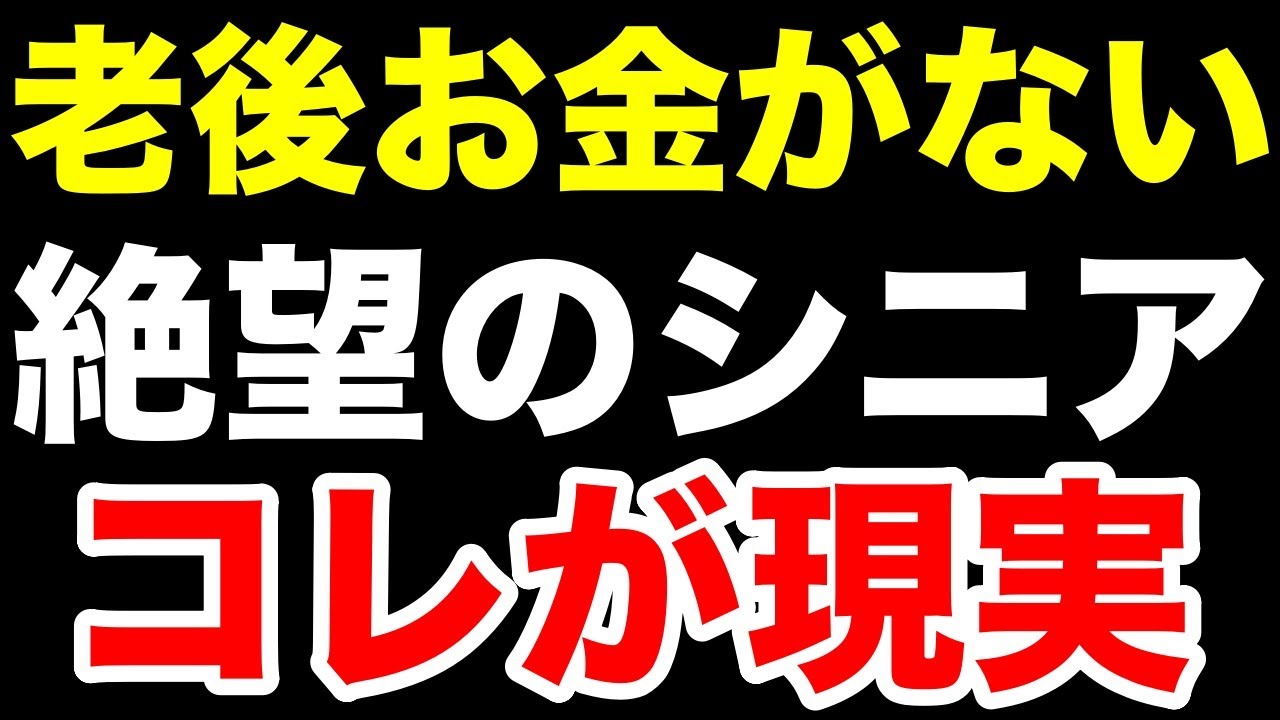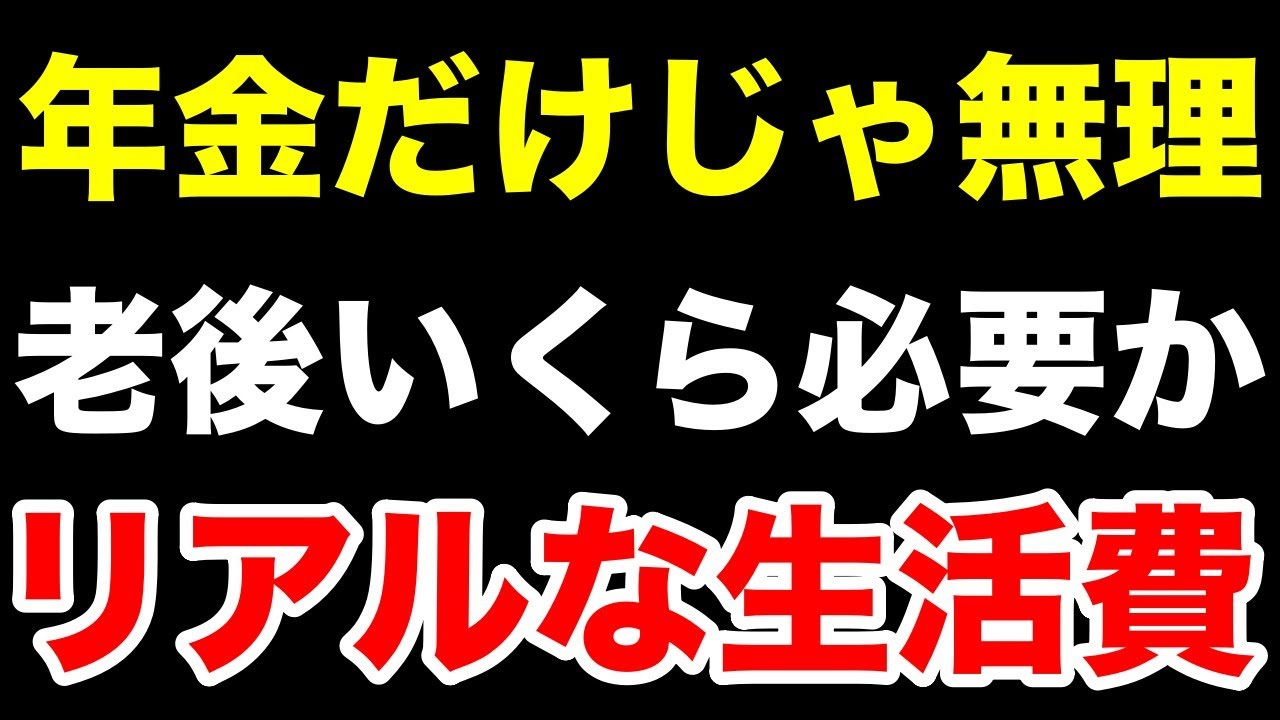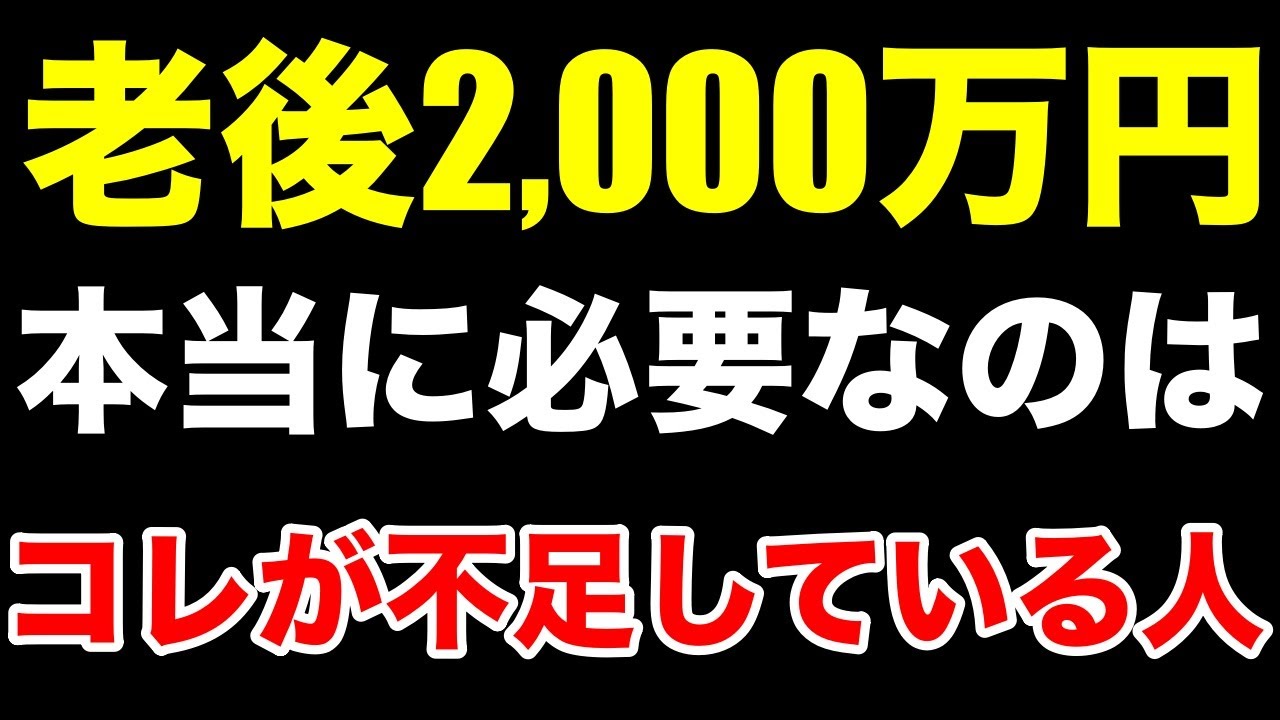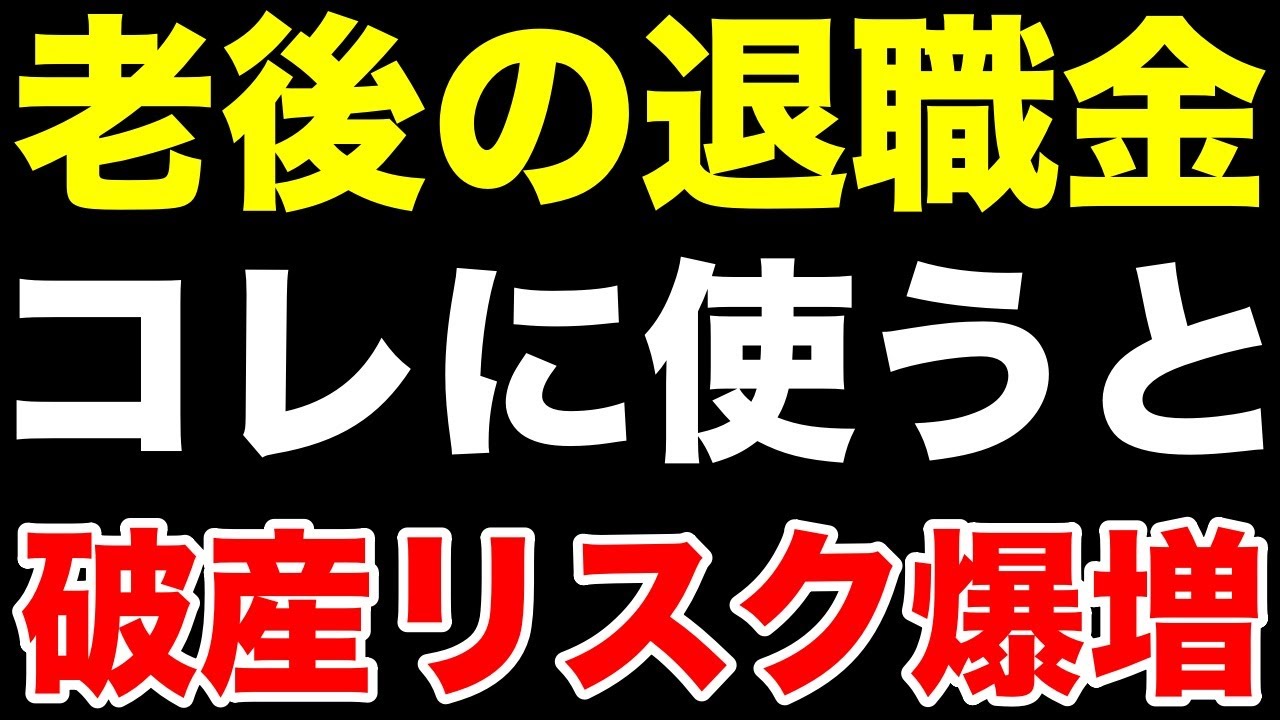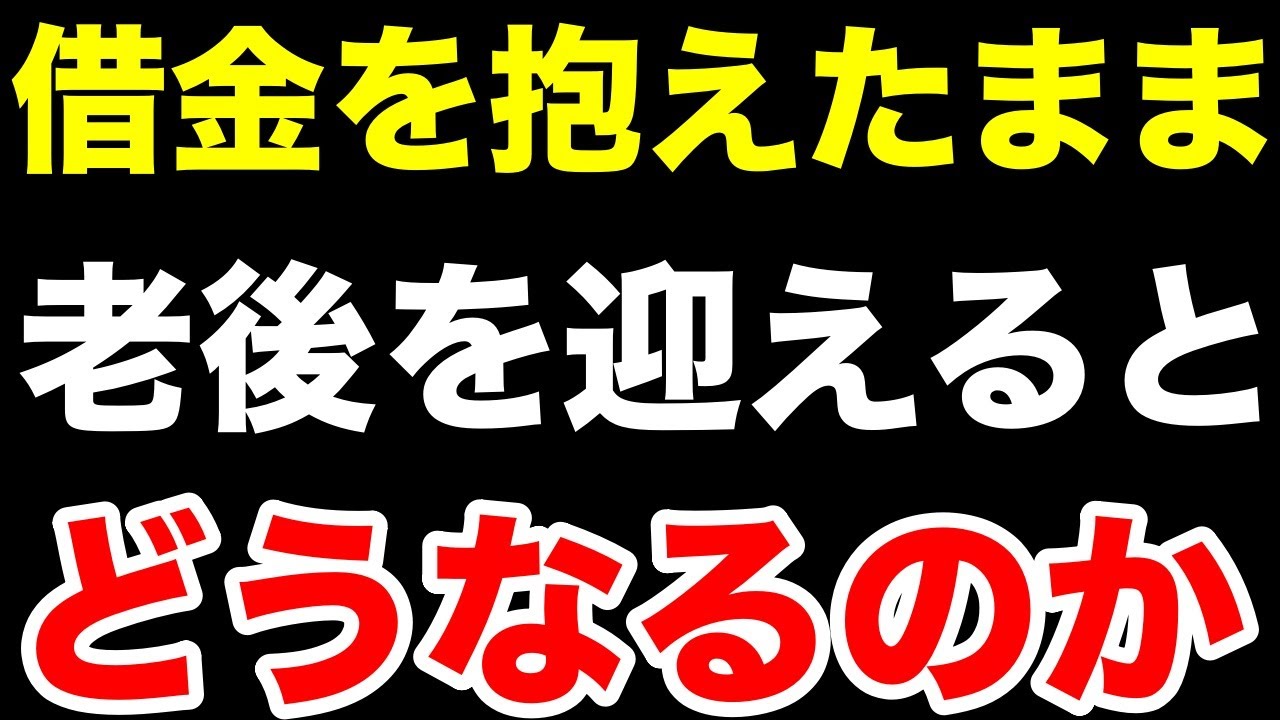老後のお金を守るために絶対にやってはいけないことを5つ紹介します!
「知らないうちにお金がどんどん減っている気がする」
「退職金や年金があるのに、なぜか将来が不安」
「これまで築いてきた貯金を、ムダにしたくない」
実はこうした不安を抱える人に共通するのが
「お金の守り方を知らない」ということです。
老後のお金は「使い方」よりも「守り方」のほうが重要です。
しかし、知らず知らずのうちにやってはいけない行動をしてしまい、
資産を大きく減らしてしまう人も少なくありません。
この記事では、
老後資金を守るために避けるべき「やってはいけない行動」5つと、そこから学べる具体的な資産防衛策を解説します。
先に結論をお伝えすると、老後のお金を守るには「詐欺や無計画な投資への対策」だけでなく、
「信頼できる人に頼りすぎない」
「必要のない保険を見直す」
「家計の見える化を行う」など、
地味だけれど確実な守りの戦略が重要です。
記事後半では、
実際にお金を減らしてしまった人の共通点や、お金を上手に守る人の考え方・行動パターンの違いについてもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
また、このチャンネル《老後コンパス》は、60代の両親をきっかけに生まれました。
父は持病と闘いながら仕事を続け、母は毎朝コンビニで家計を支えています。
『お金は大丈夫かな』
『この先働けるかな』
そんな不安を口にする二人を見て、老後はまだ先じゃなく
すぐそばにあると感じました。
そんな他人事ではない不安を、少しでも軽くするヒントを発信しています。
ぜひチャンネル登録をして、続きをご覧ください。
それでは見ていきましょう!
老後のお金を守ることは増やすよりも大切
年金+貯金があっても油断できない理由
「年金も出るし、ある程度の貯金もある。老後資金はなんとかなるはず」
そう思っている人は少なくありません。
しかし、実際に老後生活に突入してから、想定以上のスピードで資産が減っていくケースが多発しています。
例えば
・病気やケガで想定外の医療費が発生
・住宅の修繕や家電の買い替えが一気に重なる
・介護費用や老人ホームの入居準備金が突然必要になる
これらはどれも「よくあること」ですが、事前に備えていなければ、一度に数十万円から数百万円の出費になることもあります。
さらに、金利が低い今の日本では、貯金を持っていても「自然に増える」ということはまずありません。
つまり「貯めたお金をそのまま持ち続ける=目減りしていくリスク」とも言えるのです。
そしてもう一つ盲点なのが、「お金の管理」に慣れていないこと。
現役時代は給料が定期的に入ってきたため、家計に対する継続的な不安は少なかったかもしれません。
しかし、収入が限られた老後は、たとえ貯金があっても「減る一方の生活」に不安や焦りが生まれがちです。
だからこそ、老後は「増やす」よりも「減らさない」意識が何より重要なのです。
「守る意識」がない人ほど資産を失いやすい
また、老後資金を失う原因は、「お金を使いすぎた」ではないことが多いです。
多くの人が「よかれと思ってやったこと」「ちょっとの油断」「うっかりの判断」が原因で資産を減らしてしまっています。
たとえば
・「絶対に儲かる」と言われた投資話にのって損をする
・「信頼していた人」に頼まれてお金を貸して返ってこない
・「保険はとりあえず入っておくもの」と思い込み、不要な保険料を何年も払い続ける
これらはすべて、守る意識が欠けていたことが共通しています。
老後のお金は、増やすの意識だけでは守れません。
むしろ自分と家族を守るためには、
どんなリスクがあり、どこに落とし穴があるのかを知ったうえで、冷静に対処していく「守備力」が求められるのです。
お金を守る力とは、決して専門知識のことではなく、
「簡単に信じない」
「すぐに決めない」
「まず調べてみる」
といった日常の判断の積み重ねです。
現役を退いてからのお金の使い方こそ、その人の生活設計力が問われるタイミングです。
だからこそ、「やってはいけない行動」をしっかり知り、そこから「守る意識」を高めていくことが重要になります。
老後にお金を減らす「やってはいけないこと」5選
老後のお金が減ってしまう原因は、「収入がないから」だけではありません。
実は、日々のちょっとした判断ミスや、よかれと思ってした行動によって、大切な資産を失ってしまう人が多いのです。
ここでは、老後にやってはいけない5つの典型的な行動と、なぜそれが危険なのか、どうすれば避けられるのかを解説します。
それでは一つ目からみていきましょう。
① 詐欺・悪質商法を「自分は大丈夫」と思うこと
一つ目は、詐欺や悪質商法に「自分は引っかからない」と思い込むことです。
「自分は騙されない」「そんなの引っかかる人いるの?」
そう思っている人ほど、実は詐欺に狙われやすい傾向があります。
最近の詐欺は非常に巧妙で、「年金・税金の還付」「医療費控除の申請」など、もっともらしい理由をつけてお金を引き出そうとします。
また、電話や訪問販売を通じて、高齢者だけを狙った押し売りのような形で被害に遭うケースもあります。
特に、年齢を重ねると判断力や警戒心が緩みやすくなり、「信じたい気持ち」が詐欺を引き寄せてしまうこともあります。
「まさか自分が…」ではなく、常に「自分も狙われるかもしれない」という意識が、最大の防御になります。
家族や専門窓口に、ひと声かけてから判断する「ワンクッション習慣」を持ちましょう。
② 高利回りの投資話に手を出す
二つ目は「高利回り投資話に手を出す」ことです。
「年金だけでは不安だから、増やしたい」
そう思うのは自然なことですが、だからといって、根拠のない投資話や、急に紹介された高利回り案件には要注意です。
・「元本保証で月利5%」
・「いまだけ特別枠で投資できる」
・「有名人もやっているから安心」
こうした誘い文句には、誰でも心が揺らぎます。
しかし、金融庁や消費者庁は繰り返し注意喚起しており、「高利回り=高リスク」の原則は変わりません。
投資を検討する際は、まず「自分が理解できる範囲の仕組みか」「リスクはどこにあるか」を冷静に見極めましょう。
わからないものには、手を出さない。
それが老後のお金を守る鉄則です。
③ 子どもや知人に気軽にお金を貸す
三つ目は「子どもや知人に気軽にお金を貸すこと」です。
「困っているなら助けてあげたい」
親心や人情から、お金を差し出したくなる場面もあるかもしれません。
ですが、子どもや知人に気軽にお金を貸すことは控えた方がいいでしょう。
老後のお金は誰かのために用意された資金ではなく、自分が生き抜くための命綱です。
一度貸したお金が戻ってくるとは限らず、トラブルや人間関係の悪化を招くこともあります。
さらに、贈与とみなされて税金の対象になったり、介護保険や生活保護など公的制度の支給に影響が出たりするケースも考えられます。
家族を助けたいという気持ちは大切ですが、自分の将来に必要な制度を使えなくなってしまっては本末転倒です。
経済的な支援を考えるときは、制度との兼ね合いも含めて慎重に判断しましょう。
どうしても援助したい場合は、無理のない額を「渡す」と決めて割り切るか、
後日しっかり記録を残しておくなど、計画的に対応することが大切です。
「老後の資産は、まず自分の生活を守るためのもの」
という原則を忘れないようにしましょう。
④ 生命保険・医療保険を見直さず払い続ける
四つ目は「生命保険や医療保険を見直さずに払い続けていること」です。
現役時代に加入した保険をそのまま老後も継続していませんか?
生命保険や医療保険を見直さずに払い続けることで、余計な出費をしている可能性があります。
老後は現役時代と比べて、収入・支出のバランスやライフスタイルが大きく変わります。
それにもかかわらず、保険を見直さずに毎月数万円の保険料を払い続けている人も多いのが現実です。
特に、医療保険やがん保険などは、自治体の医療費助成や高額療養費制度があることを考えると、必要性が下がるケースもあります。
また、貯蓄型保険や外貨建て保険などは、途中解約による元本割れや為替リスクなど、予想外の損失を招くリスクを知っておく必要があります。
保険は「安心」を買うものですが、「内容を理解せずに払い続ける」のは、資産を減らす落とし穴になりかねません。
一度、専門家(ファイナンシャルプランナーなど)に見直しを依頼してみるのもおすすめです。
⑤ 相続・贈与の準備をしないまま放置する
五つ目は「相続や贈与の準備をしないまま放置すること」です。
「まだ元気だから、相続なんて先の話」
そう思って、相続や贈与の準備をしないまま放置していると、いざという時に家族や親族が困る事態になります。
例えば、遺言書がないまま亡くなってしまうと、預貯金や不動産の分け方をめぐって家族が揉める可能性があります。
また、生前贈与や名義変更の手続きがなされていないことで、「税金が余計にかかってしまった」というケースもあるため、早めの準備が必要です。
さらに、認知症を発症すると「自分の意思で財産を動かすこと」が難しくなり、事実上の凍結状態になってしまうリスクも出てきます。
相続や贈与の話は、気まずくなりがちですが、「自分が亡くなったあと」のためではなく、
「これから先、自分と家族が安心して暮らすため」の備えとして考えることが大切です。
早いうちから、信頼できる専門家に相談し、必要な書類や段取りを準備しておきましょう。
お金を守れる人・失う人の違いとは?
「なぜ、同じくらいの収入や貯金があっても、お金が残る人と減っていく人がいるのか?」
この疑問には明確な答えがあります。
それは、お金との向き合い方や考え方、そして日々の判断にクセの違いがあるからです。
次は、お金を守れる人・守れない人の思考と行動の違いを見ていきましょう。
まず、共通する「意識」と「行動」の差についてです。
共通する「意識」と「行動」の差
お金を守る人にはある共通点があります。
それは、目先の利益や感情に流されず、冷静に「お金の流れを見ようとする姿勢」があることです。
たとえば
・何かを買う前に「これは本当に必要か」と一呼吸おく
・よく分からない話には「とりあえず保留にする」という習慣がある
・面倒でも領収書を取っておく、明細を見るといった行動を欠かさない
一方で、お金を失いやすい人の特徴としては、
・勧められると断れない(情に流されやすい)
・「お得そう」と思ったらすぐに申し込む
・面倒な手続きや確認を避けがち
このように、資産を守れるかどうかは、性格よりも「普段の小さな選択の積み重ね」によって決まっていきます。
「自分は管理が苦手だから…」と思っている人も、意識と行動を少しずつ変えるだけで、お金の流れは大きく変えられます。
お金を信頼ではなく仕組みで管理する
お金は信頼ではなく仕組みで管理することが大切です。
「信頼していたのに裏切られた」
「家族だから大丈夫だと思っていた」
そんな声は、老後のお金トラブルでは少なくありません。
人間関係を信じることは大切ですが、お金の管理だけは「信頼」よりも「仕組み」で行うべきです。
たとえば
・定期的に家計をチェックする「仕組み」
・契約書や通帳を家族と一緒に確認する「仕組み」
・判断力が落ちてきたときに備えて、任意後見人を指定する「仕組み」
こうした見える仕組みがあることで、感情に左右されず、冷静に判断できる環境が整います。
「信じていたから話し合いをしなかった」
「確認しなくても大丈夫だと思った」
そうした思い込みが、あとになって後悔を招くこともあるのです。
大切なことは、「自分が信用している人でも、金銭に関しては仕組みで支える」という発想を持つことです。
これが、安心して老後を過ごすための土台になります。
老後資金を守るための賢い3つの行動
老後に資産を失う人の多くは、「特別な失敗」をしたわけではありません。
ほんの少しの油断や、判断の遅れが積み重なって、「気がついたら生活が苦しくなってしまった…」そんなケースがほとんどです。
では、反対に「お金を守る人」はどんな行動をしているのでしょうか。
ここでは老後資金を上手に守るために意識しておきたい3つの行動をご紹介します。
①信頼できる専門家を味方につける
一つ目は「信頼できる専門家を味方につけること」です。
老後のお金に関する判断を、すべて自分一人で行うのはかなり大変です。
年金・税金・相続・保険・介護…それぞれが複雑で、どれも人生に大きな影響を与えるテーマです。
そんなときに心強いのが、ファイナンシャルプランナー、税理士、弁護士、司法書士など、信頼できる専門家の存在です。
「何かあったらこの人に相談できる」
そう思える相手が一人いるだけで、不安や迷いはぐっと軽くなります。
もちろん、すべてを人任せにするのではなく、「専門家の意見を参考に、自分の判断軸をつくる」ことが重要です。
身近に相談先がなければ、市町村の無料相談窓口や、法テラスの無料法律相談なども活用してみましょう。
②「家計の見える化」で無駄な出費を発見する
二つ目は「家計の見える化をして無駄な出費を見つけること」です。
お金を守るうえで意外と盲点になるのが、日々の支出です。
とくに老後は「収入が少ないこと」よりも、「支出の全体像が把握できていないこと」が問題になるケースが多く見られます。
たとえば
・使っていないサブスクの月額費用
・保険料の過払い
・光熱費や通信費のムダなど
見直してみると、思った以上に無駄が見つかるものです。
家計簿アプリやエクセル、紙の家計簿でも構いません。
まずは1ヶ月だけでも「すべての出費を書き出す」と、自分の生活にどんな支出傾向があるかが見えてきます。
支出を把握することは、節約だけでなく「お金をどこに使うか」を主体的に選ぶための第一歩です。
③「使う」「貯める」「守る」をバランスよく意識する
三つ目は「使う、貯める、守るをバランスよく意識すること」です。
老後の家計管理は、「節約だけ」でも「投資だけ」でも上手くいきません。
重要なのは、「使う」「貯める」「守る」の3つをバランスよく意識することです。
・使う:心を豊かにするお金(趣味・旅行・交際など)を計画的に使う
・貯める:万一に備える生活防衛資金を一定額キープ
・守る:詐欺や無駄な出費を避け、制度を活用して資産を減らさない
この3つをバランスよく考えることができれば、老後のお金は決して不安なものではなくなります。
また、「どう使うか」を自分で選べる状態こそが、真の意味でお金に困らないということです。
不安に振り回されるのではなく、知識と仕組みで老後資金をコントロールしていきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
老後のお金を守るために「増やす」よりも「減らさない」が大事になってきます。
・老後のお金を守るためにやってはいけないこと5選
① 詐欺・悪質商法を「自分は大丈夫」と思う
② 高利回りの投資話に手を出す
③ 子どもや知人に気軽にお金を貸す
④ 生命保険・医療保険を見直さず払い続ける
⑤ 相続・贈与の準備をしないまま放置する
・老後のお金を守る賢い行動
① 信頼できる専門家を味方につける
② 家計の見える化をする
③ 「使う」「貯める」「守る」をバランスよく意識する
目先の利益や感情に流されず、やってはいけないことと、賢い行動を意識して冷静に判断する力を身につけていきましょう。
老後は、誰にとっても最初で最後の人生の旅。
わからないことも多く、不安になる日もあるかもしれません。
「老後コンパス」は、そんな旅路に寄り添う
コンパスのような存在で
あり続けたいと思っています。
これからも、あなたの役に立つ知識や気づきを
惜しみなく発信していきます。
もし「少しでも役に立ちそうだな」と感じていただけたら
ぜひ【チャンネル登録】と【高評価】をお願いいたします。
これからも「自分らしい老後」を楽しんでいきましょう!
最後までご覧いただき
ありがとうございました。