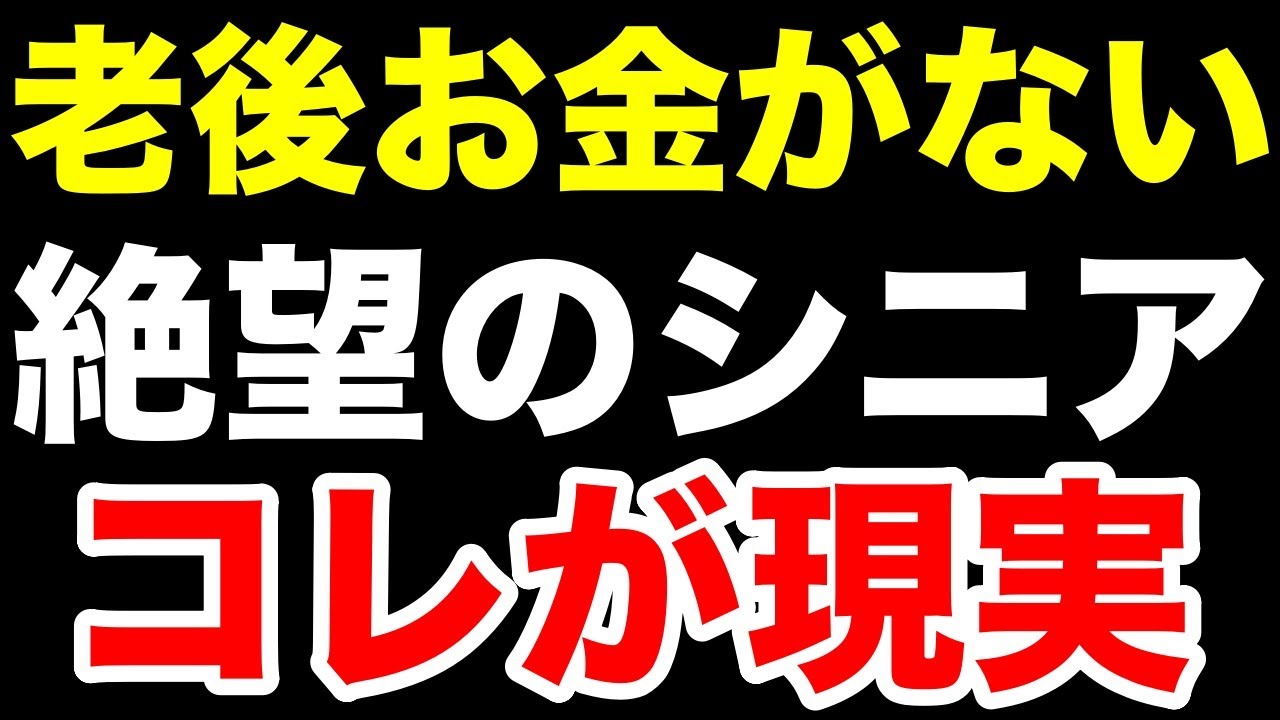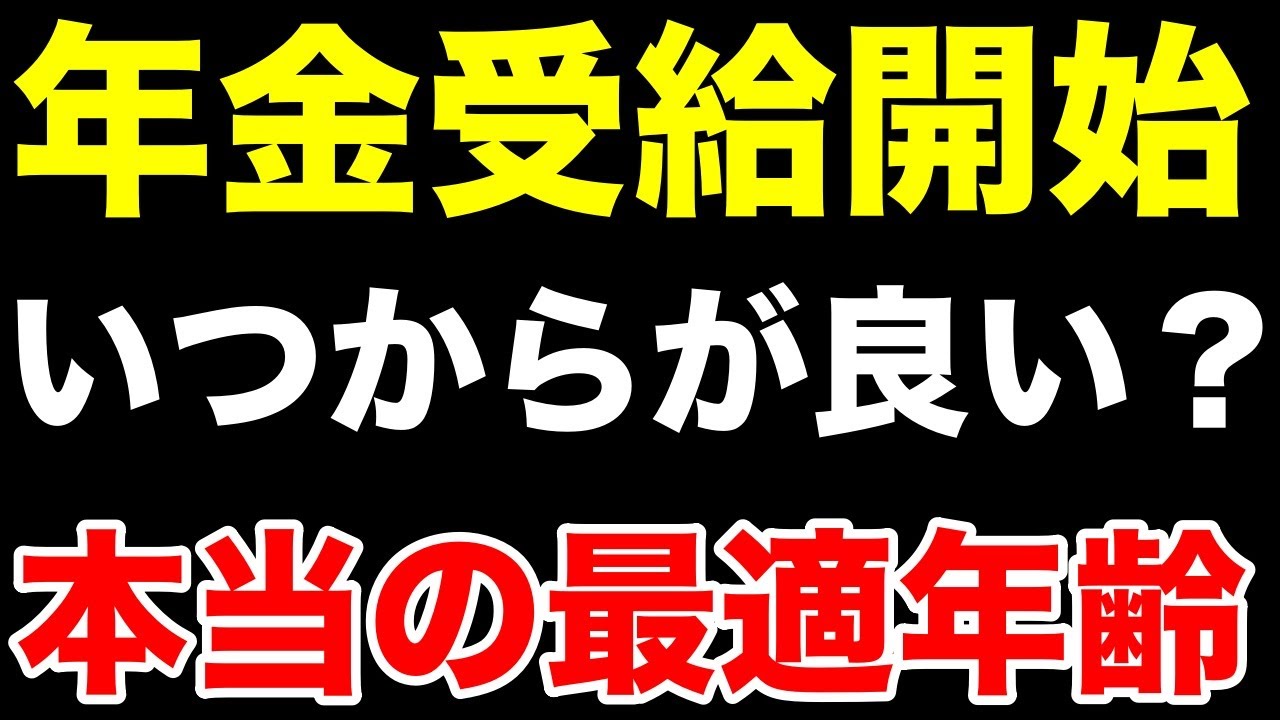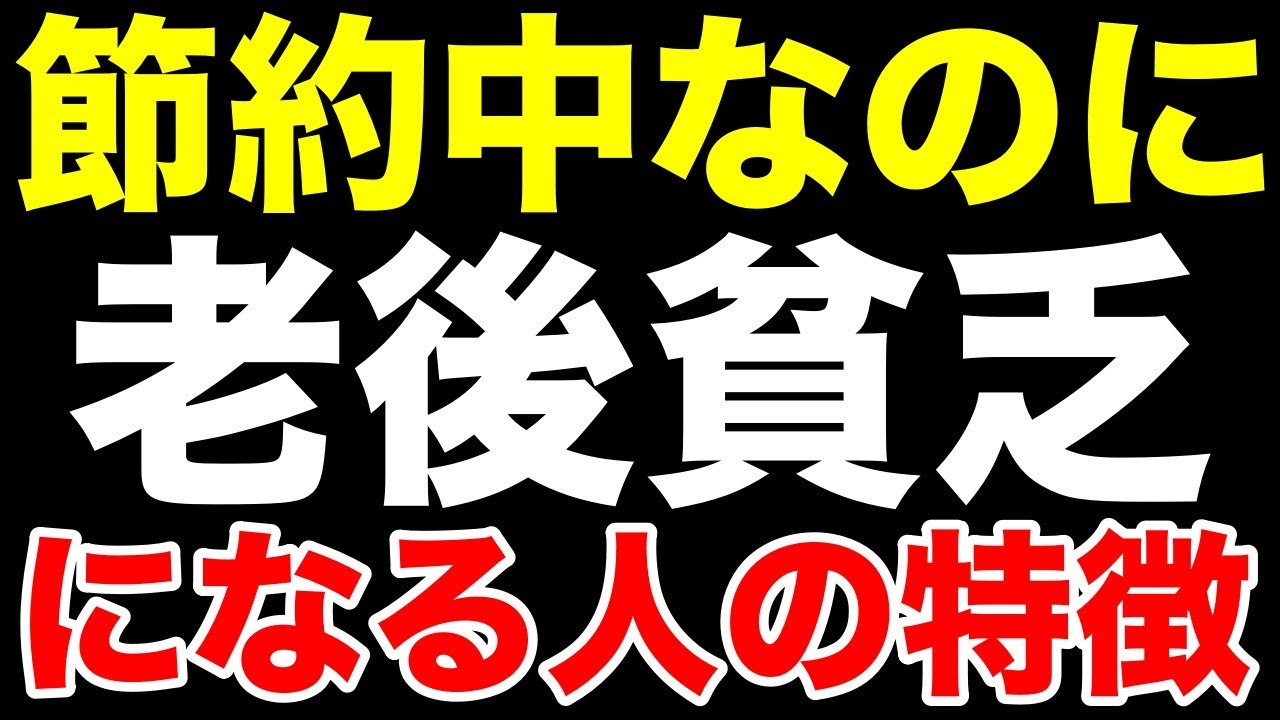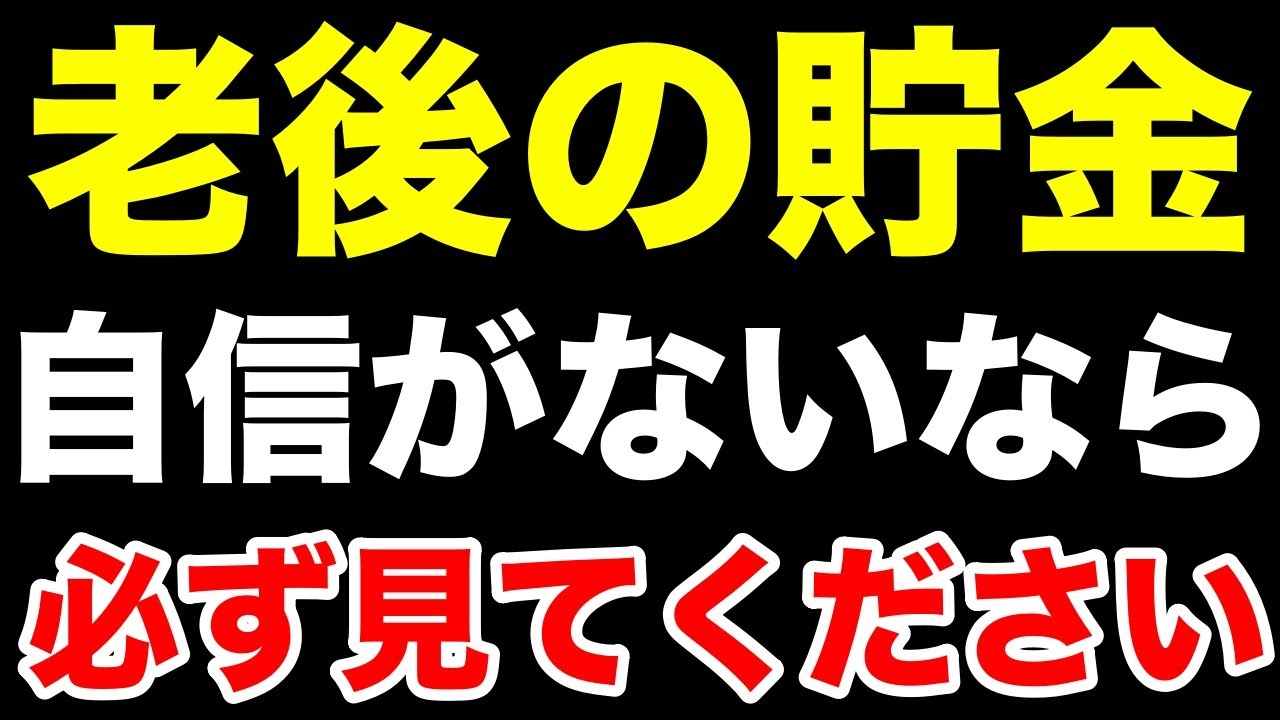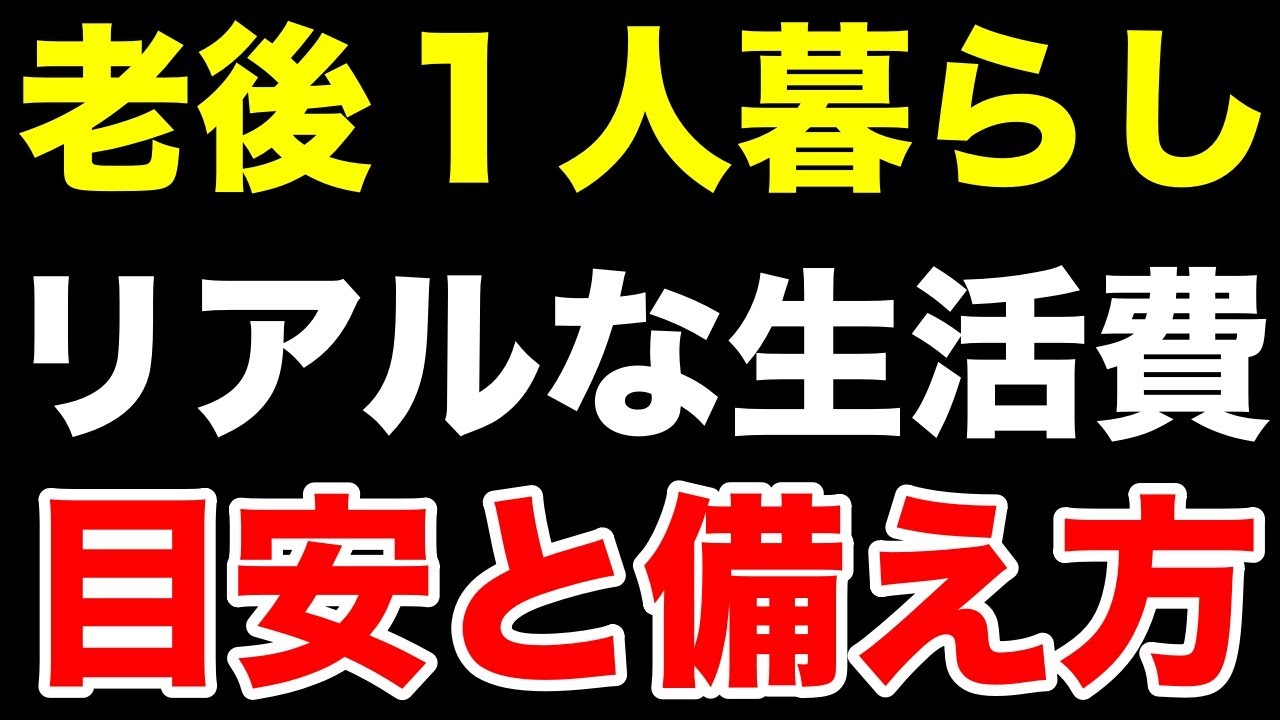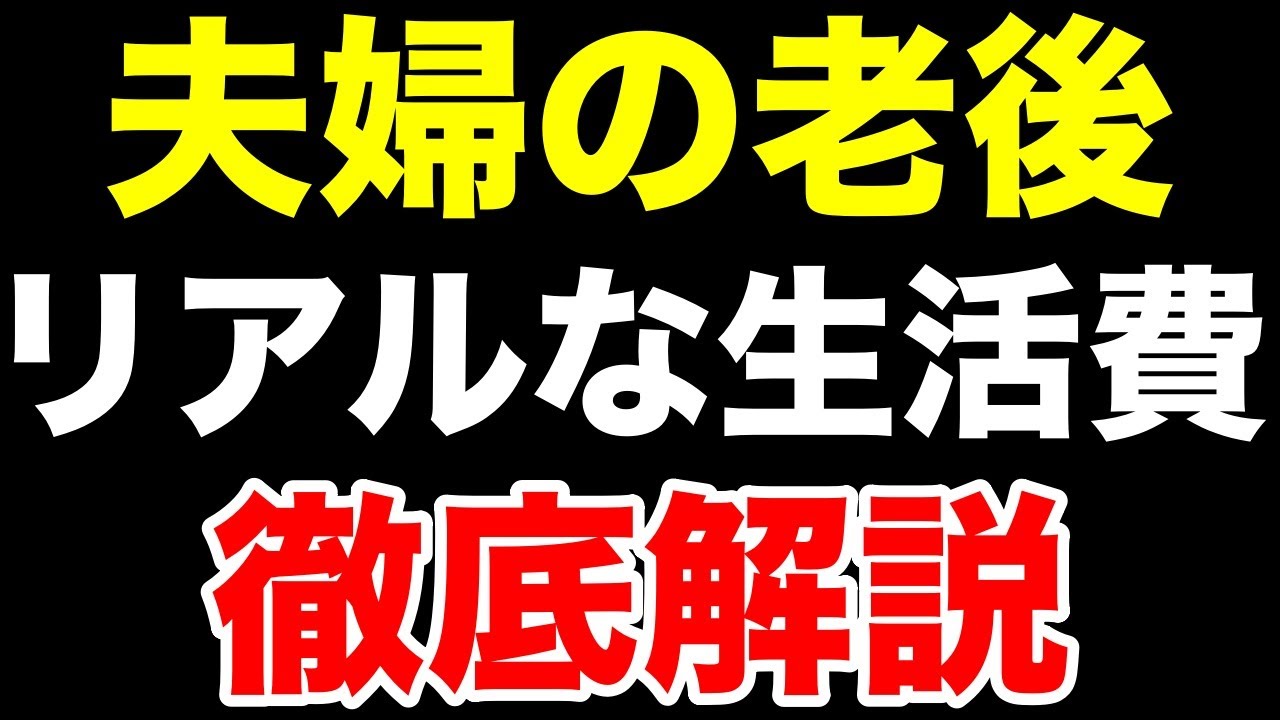【持ち家あり夫婦】老後の生活費はいくら必要?平均と安心ラインを徹底解説します!
「持ち家があるから、老後の生活費はあまりかからないと思っていた。」
「ローンも払い終えたし、年金で十分暮らせるはず。」
「でも、最近の物価や医療費の上昇を見ると、少し不安になってきた。」
実は「持ち家がある夫婦」でも、老後の生活費に悩んでいる人はとても多いです。
家賃がないことは確かに大きな安心材料ですが、その一方で、固定資産税や修繕費、医療・介護といった“見えない出費”が年々増えているのが現実です。
実際に、家を持っていても年金だけでは生活が厳しいという声が多く聞かれます。
この記事では、「持ち家あり夫婦の老後生活費」について、最新データをもとに平均額・安心ライン・不足分の補い方をわかりやすく解説していきます。
先に今回の内容の結論を少しだけお伝えすると、持ち家のある65歳以上の夫婦が平均的な生活を維持するためには、月額約28.7万円(年間約344万円)が必要です。
これは、総務省の「家計調査報告(2024年)」で示された「夫婦高齢者無職世帯」(持家率96.5%)の実支出平均286,877円に基づく金額です。
収入の平均は25.3万円のため、家賃がないとしても、実収入(年金)だけでは毎月約3.4万円が不足しており、貯蓄の取り崩しや副収入による補填が必要な現実が見えてきます。
記事の後半では、賃貸との違い、修繕・医療・介護に備える具体的な方法、そして安心して暮らすための「家とお金のバランス」についても詳しくお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
また、このチャンネル《老後コンパス》は、60代の両親をきっかけに生まれました。
父は持病と闘いながら仕事を続け、母は毎朝コンビニで家計を支えています。
『お金は大丈夫かな』
『この先働けるかな』
そんな不安を口にする二人を見て、老後はまだ先じゃなく
すぐそばにあると感じました。
そんな他人事ではない不安を、少しでも軽くするヒントを発信しています。
ぜひチャンネル登録をして、続きをご覧ください。
それでは見ていきましょう!
持ち家がある夫婦の老後生活費はいくら必要?
持ち家がある夫婦の老後生活費はいくら必要?
総務省の家計調査報告(2024年)によると、持ち家のある65歳以上夫婦の無職世帯の平均支出は月28万6877円(年間約344万円)です。
この金額には食費、光熱費、交際費、保険料、医療費など、老後の生活に必要な支出が含まれています。
一方、夫婦が受け取る平均的な年金収入は約25万円前後とされており、毎月約3〜4万円ほど赤字になる計算です。
「持ち家があるのにそんなにかかるの?」と思う人も多いですが、食費や光熱費、交際費、医療費などは現役時代より増える傾向があります。
特に、外出機会が増える退職後は、友人との会食や旅行、孫へのお小遣いなどが生活費を押し上げます。
平均データを見ても『家賃がない=出費が少ない』とは限らないのが実情です。
データを踏まえて、ローンを完済している世帯の支出シュミレーションをみてみましょう。
住宅ローン完済済みの場合の支出シミュレーション
仮に、ローンを完済していても毎月かかる支出はあります。例えば、夫婦2人暮らしで次のような支出が想定されます。
食費 6万円
光熱費 2.5万円
通信費 1.5万円
日用品雑費 1万円
医療費 1.5万円
交際娯楽費 2万円
車交通費 1.5万円
固定資産税・修繕費積立 1万円
合計するとおよそ月17〜18万円
さらに、冠婚葬祭や医療費が重なる月は簡単に20万円を超えることもあります。
年金で足りない分は、貯蓄の取り崩しやパート、年金などプラスαの収入で補う形が現実的です。
持ち家でも発生する見えない固定費とは?
こうして、月々の支出を整理してもまだ油断はできません。
持ち家には気づきにくい見えないコストが存在します。代表的なのが固定資産税、火災保険、修繕費です。
たとえば、築30年の一戸建ての場合10年ごとに100〜300万円の修繕費がかかることがあります。
屋根や外壁の塗装、水回りの交換、耐震補強などを考えると月あたり1万円程度は修繕積立として確保しておくことが理想です。
『ローンを払い終えた=家の支出が終わった』ではなく、住み続けるためのコストはずっと続くという意識が大切です。
賃貸との違い|「持ち家だから安心」と言い切れない理由
固定資産税・修繕費・保険料などの維持費
賃貸の場合は毎月家賃を払いますが、持ち家では次の費用が代わりに発生します。
・固定資産税は年間10万円前後
・火災保険は更新時に数万円
さらに、老朽化に伴い修繕費が必要になり、結果的に隠れ家賃のように年間20〜30万円規模の支出が発生します。
リフォームや建て替えの可能性をどう考えるか
維持費に加えて、長く住むほど避けられないのがリフォームや建て替えです。
住宅は時間とともに劣化するので、築30年以上経つと水回りの老朽化や断熱性能の低下などが問題になります。
快適に暮らすためには、
・キッチンや浴室のリフォーム(60〜150万円)
・屋根や外壁の塗り替え(80〜140万円前後)
などが必要です。
また、耐震性の不安やバリアフリー化を考えて建て替えを検討するケースもあります。
リフォームや建て替えのタイミングを見据えて、10年ごとに100万円、年間10万円程度を目安に積み立てておくと安心です。
家がある=現金が減らないではない現実
こうした、維持や修繕費を考えると「家がある=安心」とは限りません。
家を資産として考えるのは大切ですが、現金化しづらい資産でもあります。
実際に住み続けている限り、売ることも貸すことも難しく生活費には回せません。
持ち家は安心感をもたらしますが流動性が低い点を忘れてはいけません。
現金と家、両方のバランスを保つことが老後の安定につながります。
持ち家夫婦の生活費の内訳(1か月・1年の目安)
基本生活費(食費・光熱費・通信費など)
食費 7.6万円
光熱費 2.2万円
通信費 1万円
日用品費 5千円
交通・自動車維持費 1.8万円
これらの基本生活費だけで月13万円前後。
季節や地域によって光熱費が変動し、冬場は暖房費でさらに増えることがあります。
これらの基本支出に加えて、年齢とともに増えていく医療や介護などの変動費も無視できません。
医療・介護などの変動費
年齢とともに増えていくのが医療介護関連の支出です。
・医療費の平均は1人あたり年間13万円程度
しかし、持病がある場合はさらに上がります。
また、介護サービスを利用するようになると、月2千円〜7万円程度の負担が生じることもあります。
医療や介護関連の支出は予測することが難しいので、いかに固定費をコントロールするのかがカギとなります。
次に固定費を抑えるポイントを説明します。
固定費を抑える工夫
節約のポイントは通信費と保険の見直しです。
格安SIMへの変更、不要な保険やサブスクの解約などで年間10万円以上の節約が可能です。
・格安SIMの変更:2人で月1万円→月2千円にすると月8千円、年間9万6千円の節約
・保険の見直し:生命保険文化センター「生活保障に関する調査」から加入しすぎや重複を見直すと月3〜5千円削減できるケースが多い。年間4万5千円〜6万円の節約になる
年金だけで生活できる?不足分を補う3つの考え方
夫婦の平均年金額と実際の支出との差
総務省の家計調査(2024年)によると、夫婦高齢者世帯(65歳以上の夫婦のみの無職世帯)の平均実収入は月25万2818円です。
一方で実際の消費支出は、月28万6877円。月に約3万4000円の赤字となっています。
つまり、持ち家があっても年金だけで暮らすのは難しく、月ごとに貯蓄を取り崩すか副収入で補う必要があります。
この約3.4万円の不足は年間で約40万円、20年間で約800万円を超える計算になります。
年金額や医療費の増加を考慮すれば、この差はさらに広がる可能性があります。
では、こうした不足分は、実際にはどのように補えばいいのでしょうか。
ここからは貯金の取り崩しシミュレーションを見ていきましょう。
貯金の取り崩しシミュレーション
毎月3.4万円を貯金から取り崩すと20年で約816万円が必要です。
たとえば、定年時に2000万円の貯蓄があった場合、生活費の補填だけで半分近くが消えることになります。
ただし、支出の中には固定費の見直しで減らせる項目もあります。
食費や通信費、保険料を見直せば年間10万円以上の削減も現実的です。
また、定期的に家計簿をつけて支出を把握することも大切です。
「知らないうちに減っていた」を防ぐには、月単位でチェックする習慣が効果的です。
副収入資産活用の選択肢(年金プラスαの考え方)
近年はシニア世代でも、在宅ワークやパートで月3〜5万円を稼ぐ人が増えています。
得意な分野でのライティング、相談業、ハンドメイド販売なども人気です。
また、持ち家を活用して、資金を得る方法としてリバースモーゲージやリースバックがあります。
これらを利用すれば家に住みながら資金を得ることが可能です。
しかし、リバースモーゲージなどには注意が必要です。
詳しくはあとで説明します。
重要なのは収入源を一つに頼らないことです。
年金・貯金・副収入の3本柱をバランスよく組み合わせて、無理なく安心な生活を送りましょう。
将来のために備えておきたい出費リスト
老後の家計を考えるうえで、見落としがちなのが「将来必ず発生する出費」です。
修繕・医療・介護・相続などは避けられない支出であり、早めに金額感を把握しておくことが安心につながります。
次は、持ち家のある夫婦が老後に備えておきたい主要な出費リストです。
| 分類 | 項目 | 目安金額 | 発生時期・周期 |
| 住まい関連 | 外壁・屋根塗装 | 80〜140万円 | 10〜15年ごと |
| 住まい関連 | キッチンリフォーム | 50〜150万円 | 15〜20年ごと |
| 住まい関連 | トイレリフォーム | 15〜50万円 | 15〜20年ごと |
| 住まい関連 | 浴室リフォーム | 60〜150万円 | 15〜20年ごと |
| 生活・家計関連 | 家電・設備の買い替え | 10〜50万円 | 10〜15年ごと |
| 生活・家計関連 | 車検費 | 10〜20万円 | 2〜3年ごと |
| 生活・家計関連 | 自動車購入 | 100〜200万円 | 不定期 |
| 家族・交際関連 | 冠婚葬祭・孫支援費 | 年10〜30万円 | 不定期 |
| 家族・交際関連 | 旅行・レジャー費 | 年10〜50万円 | 不定期 |
| 健康・医療関連 | 医療費 | 月1.5〜2万円 | 毎月・継続的 |
| 健康・医療関連 | 介護費 | 月2千〜7万円 | 要介護時(不定期) |
| 福祉・住宅関連 | 高齢者施設入居一時金 | 0〜10万円 | 介護が必要になった時 |
| 福祉・住宅関連 | 月々の施設利用料 | 月15〜30万円 | 入居後 |
| 防災・保険関連 | 火災・地震保険更新費 | 5〜9万円 | 1年ごと |
| 防災・保険関連 | 介護リフォーム費 | 1〜60万円 | 要介護時 |
| 相続・終活関連 | 相続・登記・税金 | 10〜20万円 | 相続・登記時(不定期) |
| 相続・終活関連 | 葬儀費用 | 140万円前後 | 一度 |
| 相続・終活関連 | 墓地管理費用 | 墓地管理費 年1〜3万円 | 1年ごと |
これらの支出は、いつか必ず発生する未来のコストです。
月々の積立や公的制度の理解を通じて、「不安」ではなく「計画された出費」として準備しておくことが、老後の安心をつくる第一歩です。
安心して暮らすための家とお金のバランス
住み続けるか住み替えるかの判断ポイント
老後の住まいは体力・資金・立地の3つを基準に考えることが必要です。
・階段の上り下りが負担
・買い物や病院が遠く感じる
住みにくさを感じるようになったら住み替えのサインです。
築年数の古い家に住み続けるよりも駅近や平屋のマンションに移ることで、生活の質を保てる場合があります。
リフォーム費用と住み替え費用を比較し、自分たちにとってどちらが心地よい選択かを夫婦で話し合うことが大切です。
持ち家を売却して老後資金に変える方法
住み替え以外にも、持ち家を老後資金として活用する方法があります。
自宅を活用して資金を得る方法として、リバースモーゲージやリースバックがありますが、これらには注意が必要です。
リバースモーゲージは家を担保にお金を借りる仕組みですが、長生きすると融資限度額に達して「もうお金は貸せません」と言われるリスクがあります。
結果として、家を失い借金だけが残る最悪のケースもあり得ます。
また、不動産価格の下落で融資額が減額されることや、相続人の同意が必要になるなど家族間トラブルの火種にもなります。
さらに、変動金利が上昇すると返済額が持ち家の見積もり価格を上回る恐れもあります。
リースバックも一見便利に見えますが、自宅の所有権を失うため子どもに相続できなくなります。
また、家賃の支払いが発生し滞納すると退去を求められる場合もあります。
加えて、売却価格が市場より安くなる傾向があり、契約更新ができず住み続けられなくなるケースもあります。
こうしたデメリットを考えると、リバースモーゲージやリースバックは慎重に検討すべき制度です。
現実的な選択肢としては売却して資金化し、小さめのマンションやシニア向け住宅に住み替える方法があります。
所有資産をシンプルに整理し現金比率を高めておく方が、自由度の高い暮らしが実現しやすくなります。
夫婦で今から話し合っておくべきこと
こうした住み替えや資金化の方法を検討する際に、夫婦での話し合いは欠かせません。
お金・住まい・健康の3つは密接に関わっています。
どんな暮らしを望むかを夫婦で共有し、価値観の違いを早めにすり合わせておくことが重要です。
例えば、
「将来は子どもの近くに住みたい」
「旅行を楽しみたい」
「できるだけ自宅で暮らしたい」
など、具体的に話しておくと選択に迷わなくなります。
老後の安心はお金の多さではなく、夫婦の納得感から生まれます。
まとめ|持ち家があっても“油断せず備える”が安心のカギ
ここまで見ててきたように、持ち家があっても油断は禁物です。
持ち家は大きな財産であり安心材料の一つですが、それだけで老後が安泰になるわけではありません。
固定資産税、修繕費、医療費、介護費など見えない支出が少しずつ家計を圧迫します。
総務省の家計調査(2024年)によると持ち家のある夫婦高齢者世帯の1ヶ月の支出は約28万7000円、実収入は約25万3000円で毎月3万4000円の赤字です。
年金だけで生活を完結させるのは難しく、貯蓄や副収入などから補う必要があります。
大切なのは油断せず備えることです。
修繕費や医療費は必ず発生する支出と考え計画的に積み立てておきましょう。
また、助成制度や節約策を活用し家計を軽くする工夫も重要です。
さらに、夫婦で「今後どこに住むか」「どんな暮らしを望むか」を早めに話し合うことで、後悔のない選択ができます。
『持ち家がある』という安心感に甘えず、現実を見据えて行動することこそが、真の安定につながります。
老後資金の準備は早いほど選択肢が広がります。
今から一歩踏み出して安心できる暮らしを築いていきましょう。
老後は、誰にとっても最初で最後の人生の旅。
わからないことも多く、不安になる日もあるかもしれません。
「老後コンパス」は、そんな旅路に寄り添う
コンパスのような存在で
あり続けたいと思っています。
これからも、あなたの役に立つ知識や気づきを
惜しみなく発信していきます。
もし「少しでも役に立ちそうだな」と感じていただけたら
ぜひ【チャンネル登録】と【高評価】をお願いいたします。
これからも「自分らしい老後」を楽しんでいきましょう!
最後までご覧いただき
ありがとうございました。